|
○はじめに
|
|
2005年4月25日に発生した福知山線列車脱線重大事故から、3年5ヶ月が経過しました。また、2006年1月24日に発生した伯備線触車死亡事故より2年8ヶ月が過ぎようとしています。JR西日本で働く者として、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈りし、お身体や心に傷を負われた方々の一日も早いご快復を心より願って止みません。
4月には、「安全性向上計画」の総括・検証を行い、積み残された課題からなる「安全基本計画」が策定されました。私たちは、本計画を「絵に書いた餅」にするのではなく、現場から「安全風土の構築」「一日も早い社会からの信頼の回復」を第一の課題として取り組まなければなりません。
そして、JR西労組青年女性組合員全体で、JR連合が2006年5月に策定した「安全指針」を共有化し、「鉄道の社会的信頼回復」に向けた努力を続けていかなければなりません。
また、JR発足20年、JR西労組結成から15年が経過し、私たち、青年女性委員会においても、今日まで先輩方が築き上げてきた、JR西日本・JR西労組の更なる発展・飛躍を目指して、青年女性委員会らしい行動で積極的な議論で有意義な第18定期委員会にして行きましょう。
JR西労組青年女性委員会は、2008年7月1日現在、10,294名(男性7,734名・女性2,560名)で、JR西労組の約40%を占めるまでになりました。
私たち青年女性委員会は「明るく・楽しく・元気よく」をモットーに、各地本・総支部、支部、分会における青年女性委員会の組織整備や仲間作り、自主的かつ自立した青年女性委員会独自の活動に重点を置き、各級機関から指導も受けながら青年女性委員会活動を創り上げてきました。そして、今年度も引き続き「安全」についてこだわりをもち、中央常任委員会で議論し、「新大阪総合指令所組合員との意見交換会」や「各種ユースフォーラム」を開催し、「安全」について真剣に議論してきました。
また、JR西労組主催の「ユニオンカレッジ」では、「福知山線列車脱線事故」を決して忘れない取り組みの一環として、被害に遭われたご遺族の方々がJR西日本に対し、どのように思われ、感じておられるのかを、ご遺族担当をされている組合員、また事故当時事故現場で救助活動に携わることが出来ず忸怩たる思いを持った社員からの講義を行っていただき、受講生や事務局生に対し「二度とこのような事故を起こしてはならない」ということ、そしてそのために私達は何をしなければならないのかを考える時間を設けてきました。
青年女性委員会は、JR西労組の重要課題の一つでもある「次代への継承」を真摯に受けとめ、先輩方が築いてこられたJR西労組運動をしっかりと受け継ぐために、今まで以上に「継承」を意識し、具現化に向けて努力をしていくことが必要になります。
また、組織問題は避けていては何も解決しません。正しい歴史認識を持ち、むしろその「歴史」があるから今のJRや労使関係があることを正しく認識しながら、将来の運動を託される私たち青年女性委員会の視点で考え、積極的に行動していくことが必要です。
職場環境や労働条件の改善も進めていかなければなりません。「総合労働協約改訂交渉」で大幅に改善・前進しましたが、まだ完全とは言えません。これからも、男性と女性が共に生き生きと働き続けることができる職場環境や制度・条件、個々人の意識改革を含めた職場の雰囲気をつくりあげていくことが大きな課題です。先頭に立って組合員の意見を集約しながら、中央本部、地本・総支部、支部、分会といったそれぞれの単位で積極的に取り組んでいくことが求められています。
また、職場の将来展望、地方ローカル線の存続・活性化の課題、安全問題や技術・技能の継承の課題なども、今後のJR西日本の経営を大きく左右する重要な課題であり、すべて将来の私たちの家族や生活、労働条件を大きく左右する問題です。
社会的に認められる「安全」を再構築し、よりよい会社・職場と社会・地域の実現を目指し、様々な課題に真正面から取り組み、組合員が主役のJR西労組運動を青年女性委員会全員で共に創り上げていこうではありませんか。
|
|
|
○私たちを取り巻く情勢
1 経済・政治・社会情勢
|
米国のサブプライムローン(信用力の低い個人向け住宅融資)問題は予想以上に深刻で、様々な悪影響が全世界に波及しています。
欧州や日本の金融機関の不良債権拡大、米国の経済減速による各国の輸出低迷に伴う影響などのほか、金融市場を離れた投機マネーが原油市場や穀物市場に流れることで、原油や食糧の高騰の大きな要因となっている面も大きな問題です。この投機マネーの流入が、中国やインドなど新興国の原油需要の拡大、産油国側の原油増産の停滞、人口増による世界的な食糧不足といった構造的な問題や将来予測と相俟って、先高観が加速し、原油・食糧のいっそうの高騰を招いています。特に、貧しい国々に深刻な打撃を与え、社会不安を加速させるなどの問題が広がっています。世界的なインフレのリスクはますます高まっており、経済や社会へのさらなる悪影響が懸念されています。
こうした中、国連は5月、2008年の世界経済成長率予測を1月時点の3.4%から1.8%に下方修正しました。IMF(世界通貨基金)も4月に発表した世界経済見通しで、2008年の実質経済成長率は2007年の4.9%から3.7%に低下すると予測しました。米国のみならず、新興国・資源国を含めて、インフレや金融引締めなどによる成長率の鈍化が見込まれています。
また、今年は、1997年に採択された「京都議定書」の温暖化ガス排出量の削減目標の第一約束期間の初年度にあたるほか、日本で開催される7月の主要国首脳会議(G8・洞爺湖サミット)では、環境問題、なかでも「京都議定書」の期限が切れる2013年以降の地球温暖化の枠組みのあり方や、長期的な削減目標の設定などが主要議題となる予定です。「京都議定書」に参加していない最大排出国である米国はもちろん、中国やインドなど温暖化ガスの主要排出国を含めた実効ある枠組みづくりが最大の焦点となります。一方、環境対策のためにトウモロコシがバイオ燃料の原料に充当され、食糧高騰を引き起こすなどの新たな矛盾も生まれています。 |
|
1)アジア諸国の情勢
【1】難問を抱える中国の情勢
中国は、3月のチベット騒乱とこれに対する武力鎮圧をきっかけに、中国の人権問題に対して国際的な批判が高まり、各国で聖火リレーを巡る混乱が生じました。国の威信をかけた北京オリンピックは、中国にとって国際社会の信認や評価を高める重要な機会であるだけに、国際的な理解を得るためにいっそうの努力が求められます。
さらに、5月12日に発生した四川大地震は、死者が約7万人、そして今なお行方不明者が約2万人に上ります。被災者は4,500万人に上り、極めて甚大な被害が広がっています。中国は国際的な援助を積極的に受け入れるなどしていますが、救助活動は難航し、犠牲者は拡大しています。この大地震により農村部のインフラの弱さが明らかになり、中国の大きな課題である都市部と農村部との格差が露呈しました。予想以上の被害の拡大が地方の不満に繋がり、政権への不信へと拡大する危険も指摘されています。
また、2桁台の成長率を維持してきた経済成長の一方で、2008年1月〜4月の消費者物価が8.2%上昇するなど、インフレ圧力は一段と高まっており、国民の不満も高まっています。貧富の格差や公害問題など、社会の歪みも顕在化しており、中国が目指す「和諧社会」(調和の取れた社会)の実現に向けて、災害対策への取り組みと、安定した経済成長への舵取りが求められています。
5月には、胡錦涛国家主席が、中国の国家元首としては10年ぶりに日本を訪問、福田首相と首脳会談を行い、「戦略的互恵関係」を構築することで合意し、共同声明を確認しました。中国との関係改善は評価すべきであり、地球温暖化対策では中国の協力姿勢を明らかにするなどの成果も収めました。また、懸案事項であった東シナ海のガス田開発については、中国が先行開発する「白樺」(中国名・春暁)の開発に当たる中国企業に日本側が出資し、翌檜(あすなろ、中国名・龍井)」の南側の海域に共同開発区を設けることで6月に日中が最終合意しました。しかしながら、根本的な境界線問題は棚上げされ、冷凍ギョウザ問題などの懸案事項の決着も先送りされており、依然として両国間の課題も残されています。
【2】アジア各国の情勢
2月に誕生した韓国の李明博・新大統領は、米国との関係強化を打ち出し、新たな政策運営に取り組んできましたが、米国産牛肉の輸入制限撤廃を決めた後にBSE(狂牛病)への国内の反発が広がり、6月10日には全国各地で大規模集会が開催され、就任からわずか3ヶ月で支持率が急落するなど、早くも厳しい試練を迎えています。
台湾では3月の総統選挙で大勝した国民党の馬英九氏が5月20日に新総統に就任しました。馬総統は中国に対し、「統一せず、独立せず、武力を用いず」とする「三つのノー」を提示するなど、対中関係改善を重視する姿勢を明らかにする一方で、中国の民主化を促す発言や、中国の軍備増強に対抗する方針も示しており、今後の動向が注目されます。
北朝鮮は、昨年2月の6ヵ国協議の合意に基づき、5月8日にようやく核関連文書を米国に提出しました。現在、文書の分析が進められ、日米韓で対応を協議する予定です。北朝鮮は米国のテロ支援国家の指定解除と体制維持のために核問題を利用していると見られています。また日本の最重要課題である拉致問題については、日朝協議で拉致問題の再調査や日航機「よど号」ハイジャック犯など6人の引渡しへの協力を約束したことが6月13日に明らかになりましたが、経済制裁の一部解除を行うことに批判が出ています。今後、関係国と連携した実効ある外交政策が求められています。
5月2日〜3日のサイクロンで大被害を受けたビルマでは、死者・行方不明者が10万人、被災者が200万人に達する見通しで、感染症も拡大するなど、被害が深刻化しています。しかし軍事政権は被災者の救援に消極的で、海外からの援助要員の受け入れを渋る一方、政権維持を正当化する新憲法案の賛否を問う国民投票を強行するなどしており、被災者支援よりも軍政維持を優先する姿勢に対し、国際社会の非難が高まっています。
2)景気低迷が長期化する米国の情勢と大統領選の動向
サブプライムローン問題の影響は、金融不安とともに、米国内の雇用情勢の悪化、物価高騰と個人消費の減速、住宅価格の低下など、実体経済の深刻な悪化を招いています。米国経済は、依然として先の見えない状況にあり、景気停滞は長期化するとの見方も強まっています。FRB(連邦準備理事会)は、この間、利下げを続けてきましたが、景気後退とインフレの二つの相反するリスクを抱え、厳しい政策運営を求められています。また、米国の景気後退や金融危機を背景に、ドル安が進み、基軸通貨としての地位が低下してきています。米国の経済減速は、上述の通り、すでに日本を含めて世界に深刻な影響を及ぼしており、今後の動向が大いに注目されています
4年に一度の大統領選挙にむけた民主党の候補者指名選挙は長期化していましたが、5月20日にオバマ氏が事実上の勝利宣言を行い、クリントン氏は6月7日に選挙戦からの撤退を正式に表明し、予備選開始から5ヶ月あまりに及んだ民主党の指名争いは終結しました。11月に共和党のマケイン候補との間で本選挙が実施されることとなりますが、本選に向けては、経済、雇用など身近な問題への有権者の関心が高まっているほか、人種問題も争点になると見られ、今後の選挙戦に注目が集まっています。但し、環境問題については、両候補ともに地球温暖化防止には積極的で、ブッシュ政権下での米国の消極的姿勢は転換する見通しです。いずれにせよ、米国の景気減速や国際的な地位が低下する中で、新大統領による舵取りはますます厳しくなると見られます。
3)存在感を高める欧州連合(EU)とロシア新大統領の誕生
欧州連合(EU)は、米国の経済減速の影響もあるものの、新興国向けの輸出に支えられ、年率で2%後半の成長率を維持していますが、原油や食糧を中心に値上がりが続いており、消費者物価上昇率は5月で前年同月比の3.7%を記録し、1999年のユーロ圏創設以来最高となりました。ドイツやフランスでは失業率が改善し、賃上げも進んでいますが、一方で、インフレ懸念が高まっています。こうした中で、米国の金融不安などでドル安が続く中、ユーロ高が続き、基軸通貨としての地位が高まってきています。
EUでは昨年、27の加盟国首脳が、各国の首脳と欧州委員長で構成する最高意思決定機関である欧州理事会(首脳会議)を新設するなど、EUの制度強化を定めたリスボン条約に署名し、現在、各国で批准手続きが進められてきましたが、アイルランドで批准が国民投票で否決され、2009年からの条約発効の可能性はほぼなくなりました。アイルランドの国民再投票など、今後の動向が注視されます。
このほか、ロシアでは5月7日に3月の選挙で圧勝したメドベージェフ大統領が就任、同時に「統一ロシア」党首になったプーチン前大統領が首相に就きました。メドベージェフ大統領は、プーチン首相と協力し双頭体制で政権を運営する方針です。豊富な資源を背景に成長を続けるロシアですが、実体経済は、インフレや官僚の汚職など多くの矛盾や問題を抱えています。法治制度を整備し自由経済の確立を目指す新大統領が、利権勢力を抑えて改革と調和のある発展を進められるか、その力量が問われています。 |
1)転機を迎える企業業績と懸念される賃金抑制の傾向
5月中旬に相次ぎ発表された上場企業の昨年度決算では、全体としては増収増益の傾向となりましたが、2008年度の見通しは、9年振りの減収減益決算となる見通しを発表したトヨタ自動車をはじめ、多くの企業がマイナス成長を見込むなど、わが国の企業業績は減速に転じようとしています。この背景には、米国サブプライムローン問題に端を発する金融危機や米国の景気減速に伴う対米輸出の不振、原油や原材料の高騰、急速に進む円高ドル安などの深刻な要因があります。米国への輸出低迷とともに、中国など新興国の経済減速が懸念される中、外需頼みのわが国の経済成長は一層不透明感を増しています。原油や食糧などの物価上昇は継続すると見られ、米国の景気低迷の長期化などで、日本経済は踊り場、あるいは下降局面にあると見られ、当面の間は低成長が続くと予測されています。
企業はこれまで、好調な輸出を背景に業績を改善しながらも、非正規雇用の拡大や慎重な賃上げ姿勢など、労働分配率を抑制して成長を維持してきました。この結果、好調な企業業績が家計に反映されず、個人消費は低迷し、内需主導の自律的な経済成長が阻まれてきたことは明らかです。業績の悪化を見通し、今夏の主要企業のボーナス支給額はほぼ横ばいになると見られ、賃金抑制の傾向がさらに鮮明になっています。しかし、自律的、持続的な景気拡大の実現には、輸出や人件費抑制で経営体力を蓄えてきた企業が、雇用や賃金の健全化など、適正な労働分配を通じて個人消費の回復を図ることが不可欠であり、そのための経営方針の転換が求められていると言えます。
2)雇用・労働の課題の顕在化と物価上昇による悪影響
7月の主要国首脳会議(洞爺湖サミット)を前に、5月11日から13日まで、主要国労働担当相らが集まる「労働サミット」が新潟市で開催されました。この中で、連合・騠木会長は、非正規雇用の規制緩和に関する認識について、「ワーキング・プア」を生み出す要因となった労働者派遣法改正などに触れ、大手企業が派遣法違反を繰り返してきた実態も指摘しながら、経営側を厳しく批判しました。世界的にも雇用の悪化や格差の拡大などが広がる中、かつて、日本的な長期雇用により社会の安定を維持してきたわが国の風土は一変し、情勢は急激に悪化しています。さらに、この問題に対する経営側の理解は浅く、労使の認識の乖離が大きいことも深刻な問題です。
企業の人材確保の必要性や、4月から施行された改正パート労働法の影響などにより、この間、減少し続けてきた正社員の数はようやく増加に転じつつあります。3月の厚生労働省勤労統計調査によると、前年同月比で、正社員が2.3%増加したのに対し、パート労働者は0.8%増にとどまる結果になりました。しかし、1,700万人を超えて全雇用労働者の1/3を占める非正規社員の低賃金、不安定雇用の実態を改善するには程遠い状態にあります。パート、派遣労働者の問題のほか、「偽装請負」「サービス残業」「名ばかり管理職」など、雇用、労働に関わる問題が連日のように報道され、企業の法令違反が指摘されているのが実態です。
また、ガソリンや食料品などの値上がりも深刻化しています。総務省が発表した4月の消費者物価指数(生鮮食品除く)は、暫定税率の期限切れでガソリンが値下がりしたものの、前年同月比で0.9%上昇、7ヶ月連続で上昇が続いており、今後のインフレリスクも高まっています。レギュラーガソリンの全国平均店頭価格は、6月16日時点で1リットル172.3円となっています(石油情報センター発表)。生活必需品の値上がりは、一般家計を直撃し逆進性が高く、自動車依存度の高い地方への影響も大きいなど、格差を助長する要因にもなっています。賃金抑制と物価上昇とが相まって、家計はいっそう厳しくなってきています。
3)リーダーシップが問われる地球環境問題への対応
7月の主要国首脳会議(洞爺湖サミット)で議長国を務めるわが国は、実効性のある国際合意をまとめるためにも、国内の温暖化ガス削減の決意と有効な具体策を明らかにする必要があります。福田首相は6月9日の会見の中で、洞爺湖サミットに向けた日本独自の地球温暖化対策「福田ビジョン」を発表しました。温暖化ガスの排出枠を売買する排出量取引制度を今秋に試行的に実施する方針を表明し、中期目標として2020年までに「14%削減が可能」と初めて数値に言及しました。
しかしながら、排出量取引については、日本経団連をはじめ慎重な意見が出されているほか、温暖化ガス削減に向けた中期的な具体的取り組みは示されていません。「京都議定書」の目標達成(1990年比で温暖化ガス排出量を2008〜2012年平均で6%削減)を確実にするとともに、ポスト京都議定書での中期目標と、その実現のための方策を明示し、サミット議長国として世界を納得させることのできる決意と実行力が問われています。
4)年金・医療・道路特定財源などで高まる政府への不信
年金記録漏れ問題などで年金制度への不信は極限にまで高まっています。政府・与党は今秋には基礎年金の国庫負担を1/3から1/2に引上げる方針ですが、急速に高齢化が進む中で、抜本的な改革にはなりません。また、本年4月からは、75歳以上の高齢者を現役世代から分離し、年金から保険料を徴収するなど、高齢者本人にも負担を求める「後期高齢者医療制度」が導入されました。相次ぐ手続きミスもあり、高齢者からの不満が大きく、政府・与党は、年金収入が低い人の保険料の90%軽減や年金から天引きされる保険料の家族の肩代わりなどを柱とする修正案に6月12日に合意しましたが、制度根幹は維持されており、批判鎮静化の見通しは立っていません。民主党をはじめ野党4党は、5月23日に参議院に制度廃止法案を提出したほか、年金記録漏れ問題の実態解明に向けた国政調査権の発動も検討するなど、医療・年金問題を焦点に、政府との対決姿勢を鮮明にしています。
道路特定財源を巡っても迷走が続いています。政府は年間5.4兆円ある道路特定財源制度を2009年度から一般財源化する方針を閣議決定し、2008年度から10年間で総額59兆円を投じる「道路整備中期計画」も見直すこととしています。しかし、5月13日、参議院で否決された、道路特定財源を10年間延長する「道路財政特別措置法」が衆議院で再可決されました。この法律は、閣議決定と全く矛盾する内容です。民主党の追及で、道路計画の杜撰な需要想定や、道路特定財源の不適切な支出なども明らかになり、国民の政治不信は高まっています。自民党内には反対の意見がくすぶり、一般財源化を骨抜きにする動きが懸念されるほか、一般財源化を睨んだ省庁間での予算の争奪戦も始まっています。このような状態で、本当に無駄な道路建設を取り止め、中央による地方のコントロールを廃し、効率的な財政運営が出来るのか、疑問視せざるを得ません。
5)急落する内閣支持率と総選挙の必要性
昨年7月の参議院選挙で民主党を中心とする野党が過半数を握ったことによる、いわゆる「ねじれ国会」は、国会運営において多くの変化をもたらしています。年金・医療問題や道路特定財源問題では、長年の税金の無駄遣いや政官癒着の構造にメスが入りました。日本銀行の総裁人事の否決を巡っても、天下り人事の慣例化に一石が投じられたことは間違いありません。また、道路特定財源の揮発油税などの暫定税率の維持を盛り込んだ「租税特別措置法改正案」が参議院で成立せず、4月から、与党が衆議院で再可決するまでの1ヶ月間、ガソリンの値下げが実現したことも、従来では考えられない変化です。さらには、6月11日には、現行憲法の下で初めてとなる首相問責決議案が参議院で可決されました。
4月27日に実施された衆議院山口2区の補欠選挙では、後期高齢者医療制度や暫定税率・道路特定財源の問題が焦点となり、民主党候補が大差で勝利を収めました。また、6月8日に投開票された沖縄県議選で与党が過半数割れするなど、有権者の不信は高まる一方です。福田内閣の支持率も、5月の世論調査では20%前後まで急落しています。政府・与党は、国民不信の高まりに、解散・総選挙すらできない状態に陥っていますが、今秋には道路特定財源の一般財源化をめぐる税制改正の正念場を迎えるなど、政局は極めて不透明になっており、新首相の選出で活路を模索する動きも見受けられます。いずれにせよ、国民に支持されていない内閣は、一刻も早く総辞職し、選挙で民意を問うのが当然だと言えます。その結果、8月1日に内閣改造を行ったばかりの「福田内閣」は突如9月1日に首相を辞任するという事態が発生しました。安倍前首相と同じく、またしても政権を投げ出した形となり国民不在の政治状況があると言えます。その後、与党・自民党では、5人の候補者による自民党総裁選挙に立候補し、結果、麻生氏が自民党総裁に選出され、9月24日には首相指名を受け、第92代、59人目の首相に就任しました。
衆議院総選挙の日程は定かではありませんが、選挙態勢を強化するとともに、民主党中心の政権奪取に向けて取り組む必要があります |
|
1) 2007年度決算
2007年度決算は、N700系の投入や「のぞみ」の増発などにより、新幹線を中心に運輸収入が増加し、関連事業も好調に推移した結果、連結営業収益(前期比2.2%増)、連結経常利益(同4.5%増)ともに過去最高を記録し、5期連続の増収増益となりました。運輸業では、新幹線が前期比4.5%増と5期連続で増加したほか、在来線(その他)の運輸収入が5千万円の増収となり、平成7年以来12年振りの増収となりました。関連事業では流通業、不動産業などが好調でした。
自己資金による設備投資は単体で1,596億円であり、うち安全投資は998億円となっています。
2)2008年度の経営見通し
2008年度の連結通期業績予想は、営業収益(12,980億円)、経常利益(1,148億円)、当期純利益(640億円)とも過去最高を見込み、年間配当7,000円を計画しています。また、自己資金による設備投資については、連結で1,750億円(うちJR西日本1,350億円)を予定しており、そのうち安全関連投資については、地上設備が2007年度を上回るものの、車両の老朽取替が少なくなる分、全体額として2007年度より減少する見込みです。
3)JR西日本グループ中期経営計画2008−2012
現在の中期経営計画「チャレンジ2008」は福知山線列車脱線事故以降、平成18年度に見直したものですが、「安全基本計画」を策定したことや連結ROA(総資産営業利益率)・連結ROE(自己資本当期純利益率)が平成20年度に達成する見込みなどから、新たに「JR西日本グループ中期経営計画」を策定しました。5年後の平成24年度の営業収益は14,300憶円を見込んでいます(詳細は「(3)具体的な運動の展開」) |
|
<JR西日本の経営実績の推移>
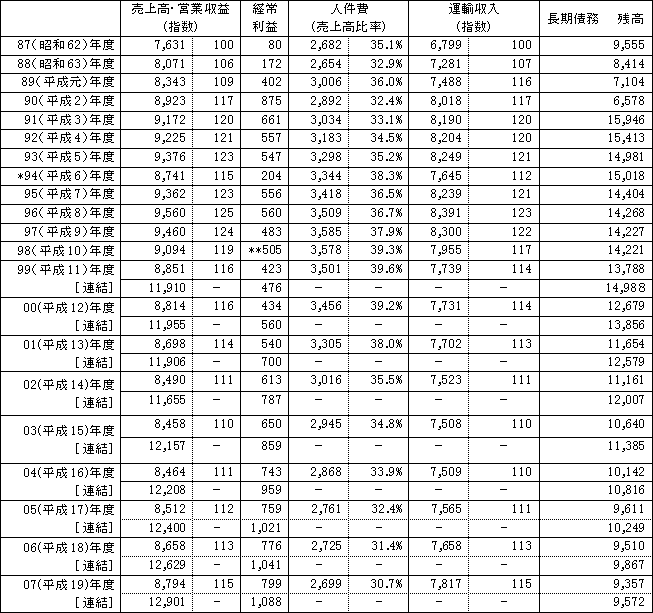
*94年度:阪神大震災
**98年度から会計制度が変更、事業税が営業経費から除かれたため、経常利益が増加。 |
JR各社の2007年度決算は、JR東日本、東海、西日本の本州三社とJR九州は、鉄道業・関連事業ともに好調で、増収増益を記録しました。特に本州三社は堅調な経営を持続しています。JR四国は11期振りに鉄道運輸収入が増加し、単体では増収増益決算となりました。JR貨物はモーダルシフトの加速で収入増が続いています。一方、JR北海道は減収減益決算となりました。JR三島・貨物会社は明るい要素もあるものの、依然として経営をめぐる環境は厳しく、各社間の経営体力の差はさらに拡大してきています。
来年度は、景気減速を予測して、JR東海、九州、北海道で減収減益決算を見込むなど、厳しい見通しも示されています。
1)JR東日本
鉄道運輸収入の伸びや関連事業収入の増加により、2007年度決算は、売上高(前期比1.7%増)、経常利益(同12.2%増)ともに過去最高を記録、3期連続での増収増益となりました。在幹を合わせた輸送量が前期比2.3%増加し、運輸収入は新幹線が同2.4%(115億円)増、在来線が同1.5%(180億円)増となりました。関連事業では、駅スペース活用事業などが好調に推移しています。来年度は、売上高1.8%増、経常利益1.9%増と引き続き増収増益決算を見込み、年間配当11,000円を計画しています。
2)JR東海
2007年度決算は、N700系の積極的な投入などで鉄道の輸送量・運輸収入ともに増加し、関連事業も好調で、5期連続の増収増益(売上高・前期比4.6%増、経常利益・同16.7%増)となりました。中でも新幹線の運輸収入は前期比4.1%(426億円)増を記録しています。長期債務も当初計画の1.5倍を縮減し、財務体質の改善も進みました。来年度は減収減益を見込んでいますが、年間9,000円の配当を計画しています。
3)JR北海道
2007年度決算は、鉄道運輸収入が4年連続で増加したものの、旅行子会社の店舗廃止などで売上高は前期比0.5%減となったほか、経営安定基金運用益も過去最低の平均金利を記録し減少、経常利益は同54.0%減の減収減益となりました。来年度は本体が11年振りの赤字計画となることで、連結でも減収減益決算と見込んでいます。
4)JR四国
2007年度決算は、単体では売上高が11期振りに増加に転じ(前期比0.9%増)、経常利益も増加(同15.5%増)し、増収増益を記録しました。鉄道運輸収入は、島内の減少が続く一方、本州との輸送量が増加し、前期比0.3%増と11期ぶりに増加しました。来年度は、連結・単体ともに減収増益決算を見込んでいます。
5)JR九州
売上高は昨年5月のドラッグイレブンHDの子会社化や鉄道事業の増収などで前期比17.1%増、経常利益は同4.7%増となり、2007年度決算(連結)は6期連続の増収増益となりました。売上高、経常利益は過去最高を記録し、経営は好調に推移しています。鉄道運輸収入は前期比で1%増加しました。なお、来年度は減収減益決算を見込んでいます。
6)JR貨物
2007年度は、中越沖地震などの輸送障害で列車の運休本数が拡大したものの、モーダルシフトの加速でコンテナ輸送が増加(収入は前期比2.4%増)したほか、不動産収入が増加するなどした結果、増収決算となりました。しかし、線路使用料の増など営業費も膨らみ、経常利益は減少しました。なお、来年度は増収増益決算を見込んでいます。
|
|
| <JR7社の2007年度決算> |
| ※上段:単体、下段:連結、()内は前年増減・%、単位:百万円 |
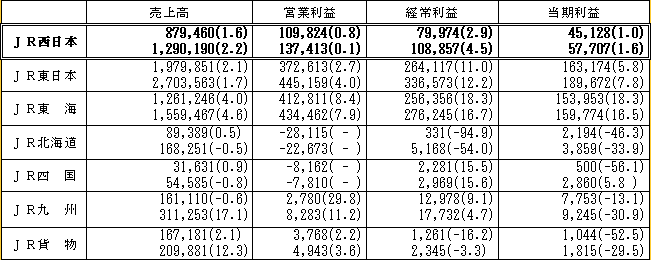
|
| (3)労働界の動向 |
|
【1】非正規雇用労働者と格差是正に向けた連合の取り組み
|
|
連合は昨年10月に第10回定期大会を開催し、2年間の運動方針を決定するとともに、騠木会長を先頭とする執行部を選出しました。騠木会長は挨拶で、特に非正規雇用労働者の問題を運動の柱の一つに据え、国民的な視野の広がりを求めながら全力を尽くす決意を表明したほか、格差是正について、不条理な格差や不公正・不公平な格差の存在を許さない姿勢で取り組む決意を明らかにしました。運動方針では、(1)加速化する「使い勝手の良い労働」への対応、(2)中小・非正規労働者を含む、働く者全ての連帯と組合員に共感の得られる運動、(3)働き方の改革と「労働を中心とした福祉型社会」の構築、などが力点として設定されています。
連合は、格差社会の最大の原因は非正規雇用問題の急速な増加にあり、総じて低処遇で、年収が200万円に達しない「ワーキング・プア」といわれる労働者を生む要因となっているとの認識に立っています。連合内に「非正規労働センター」を設置し、処遇の改善、労働者派遣法見直しなど働き方のルールの是正、非正規雇用労働者の組織化やネットワークづくりなどに取り組んでいるところです。5月に開催された、前述の「労働サミット」で、騠木会長が経営側を厳しく批判したように、非正規雇用格差問題に対しては、連合と経営側との認識の差が明らかになっており、真の課題解決のためには、厳しい実態を訴え、国民世論を喚起する広範な運動が求められていると言えます。
なお、こうした方針と姿勢に基づき、2008春季生活闘争で連合は「生活の維持向上を目指し、社会的な分配のあり方に労働組合として積極的に関与し、内需拡大などマクロ経済への影響力を発揮する」ことを目標に掲げ、各構成組織が精力的な交渉に取り組んできました。しかし、賃金については、中小組合で昨年を上回る結果を獲得した組合も多く、パートの労働条件改善の成果もありましたが、賃上げは昨年度をわずかに上回ったものの、残念ながら、労働分配率の引き上げと個人消費の改善という目的は果たせませんでした。
また、昨年12月に発表された厚生労働省「平成19年度労働組合基礎調査」によれば、わが国全体の労働組合員数は13年振りに減少から増加に転じ、昨年より3.9万人(0.4%)増加し、1,008万人となりました。一方、推定組織率は、雇用者数の増加によって0.1ポイント低下して18.1%になりました。組織率は31年連続で低下しましたが、連合の組合員数は、昨年より10.1万人増加して675万人となるなど、ようやく組織減少の傾向には歯止めがかかったといえます。
まじめに働く国民を愚弄する政府・与党への不信や反発は極限にまで高まっています。昨年7月の参議院選挙での民主党の躍進に続き、来るべき衆議院総選挙で、わが国最大の社会勢力である連合が存在感を発揮し、政権交代を成し遂げ、私たちの勤労者の声を反映する政治を実現することが求められています。 |
|
| JR連合が加盟する交運労協(ITF−JC)は昨年10月4日、「力と政策で、人と環境にやさしく、安全で安心して利用できる輸送サービスを確立しよう!」をスローガンに、第23回定期総会を開催しました。交運労協はわが国の基幹産業である交通運輸産業に働く者の政策集団として約65万人を組織し、公共交通の安全確保や政策実現などに向けて取り組みを進めています。政策・制度要求の取りまとめと省庁要請行動に力を入れており、特にツアーバス対策については、JR連合自動車連絡会が主導する運動と連携してきめ細かな取り組みを進め、国土交通省の対策に繋げるなど、大きな成果を収めています。2月22日には、バス・タクシー・トラック事業者には実質値上げとなる首都高速・阪神高速道路距離別料金に反対する集会とデモ行進を都内で開催しました。また、国際活動については、ITF(国際運輸労連)の日本事務所として、国際連帯活動への参加などの取り組みを推進しており、JR連合は構成組織の一員として、活動に積極的に参画しているところです。 |
|
1999年にJR連合が「民主化闘争宣言」を発してから、今年は10年目となります。JRの労働界は、JR連合が最大産別(7万4千名)としての地位を確保してはいるものの、JR総連(6万9千名)、国労(1万6千名)の三極に、残念ながら今なお分化しており、特にJR東日本、JR北海道、JR貨物では、JR総連が多数を占めるという偏った勢力構成が続いていることは厳然たる事実です(人数は厚生労働省「平成19年度労働組合基礎調査」)。
JRの労働組合の分裂は、連合をはじめとする労働界や社会の中で、JRの労働運動の地位の低下を招き、私たちの意見や要求の反映の阻害要因になっているほか、JRが労働組合の健全な社会的役割を発揮することを妨げる大きな原因にもなっています。上記三社のJR総連系の第一組合では、組織への服従、言論の封殺、反対者の弾圧などの非民主的な労働運動が進められてきた結果、一般の組合員は、労働組合や組合役員に対する嫌悪感や反発が生じ、本来の労働組合の意義や役割が理解されないという、消極的、退廃的な労働組合観や勤労観が広がっていると危惧されます。
しかし、JR連合のこの間の責任ある運動により、私たちは、JRの代表産別としての社会的な地位や評価を固めてきています。情勢が極めて有利に急展開する中で、確実に民主化闘争の最終段階が近づきつつあると分析出来ます。 |
|
| [JR各社の労働組合の組織構成] |
|
※グループ労組除く、()内は正社員以外[2008年4月1日現在・JR連合調べ]
|
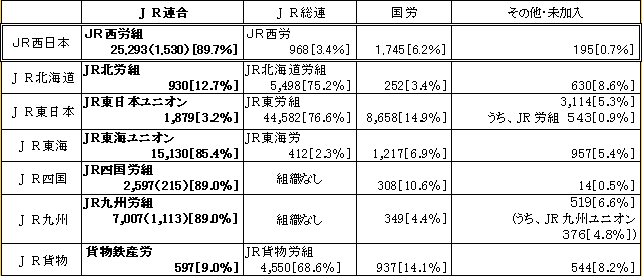
1)弱体化が急速に進むJR総連・東労組の動向
昨年7月17日に「浦和電車区脱退・退職強要事件の刑事裁判」の一審で被告7名全員に有罪判決が下され、これを受けて、JR東日本が8月30日に社員籍のある6名全員を懲戒解雇したことを契機に、JR総連・東労組は徹底して追い詰められ、急速に弱体化が進んでいると言えます。JR東日本への対決姿勢を鮮明にするJR総連とは対照的に、労使関係の当事者である東労組のトーンは低く、完全に守勢に回っており、産別と単組との姿勢の差が顕在化していることも興味深いところです。
労使関係では、JR東日本の懲戒解雇処分に対し、東労組は、清野社長宛の抗議署名や、36協定の締結や「ライフサイクルの深度化」施策などをめぐる抵抗闘争などを行い、加害者である被告7名を「美世志会」と称して、表面上は勇ましく演じていますが、いずれも成果は上がっていません。また、会社は業務掲示や社長挨拶などで職場規律の遵守を繰り返し厳しく訴えており、東労組はさらに封じ込められつつあります。社員籍のある解雇者6名の「地位保全仮処分申立」に対して、東京地裁は昨年12月25日、地位確認は却下したうえで、賃金の一部の支払と社宅使用を命じましたが、会社は異議を申し立てて全面的に争う姿勢を示しています。東労組側は本訴を提起した模様ですが、今後の動向が注目されます。
また、浦和事件の刑事控訴審は、3月末に東労組側が「控訴趣意書」を提出し、今後、東京高裁で審理が進むと見られますが、強要行為の事実は明白であり、再び敗訴することは確実です。組合員や社会の離反が進み、ますます追い詰められる彼らは、組織の終焉に刻一刻と向かっているものと分析されます。
こうした動向を背景に、組織内部では、新潟地本、長野地本を中心にJR労組の大量脱退を招き、2月7日の東労組中央委員会では200名近い役員らの制裁を行うなど引き締めに躍起となってお
り、彼らの異常性がますます明らかになっています。新たに成立させた新潟地本、長野地本の執行部は、助役など会社管理者で組織する管理部会役員や支社主席が委員長や書記長に就き、さらに、JR総連・東労組の中心課題であるはずの「美世志会」運動とも距離を置くなど、会社に迎合して組織の温存を懇願する状況にあるようです。
また、6月1日〜2日にJR総連の定期大会が開催された模様ですが、三役が総退陣したほか、浦和事件被告2名とJR東海蒲郡駅事件被告1名が専従執行委員として選出されるなど、「懲戒処分者救済」執行部の色彩が濃厚になっています。
さらに北海道労組、貨物労組では、東労組の弱体化を背景に、「美世志会」運動を旗印とするJR総連運動への追従を強制され、組合員に不満と矛盾が高まっています。貨物労組の緒方委員長は、1月の労働雑誌のインタビュー記事で、徐行区間の速度超過や早発を容認し開き直るという、安全軽視の発言を行いました。5月22日には参議院国土交通委員会で山下八洲夫議員(JR連合国会議員懇談会副会長)がこの問題を含めてJR貨物の安全問題について国土交通省の認識を質し、冬柴大臣は「(労組)幹部の発言も適切でない」と答弁しています。
有利な情勢を活かし、JR連合は、JR総連・東労組の職場における集団的糾弾行動の被害者である三鷹電車区事件の佐藤久雄氏の運転士復帰と、浦和電車区事件の吉田光晴氏の復職を求める裁判闘争をはじめとする「被害者救済」「信頼づくり」の運動を進めてきました。この運動に対する内外の理解の輪が広がり、両事件ともに、解決への道は着実に進んでいます。このように、私たちの取り組みは、まさに大きく結実しようとしています。
このほか、組織拡大も、決して十分とは言えませんが、JR東日本ユニオンが1年間で19名の新たな仲間を迎えたほか、JR北労組、貨物鉄産労でも組織拡大を果たすなど、着実に成果を収めています。
2)不採用問題解決の行方が見えない国労の動向
国労は「1047名不採用問題」の解決を中心課題に運動を進めていますが、政治解決できる内部の環境が整っているとは言えず、さらに、裁判闘争も迷走するなど、依然として解決の行方が見えない状況が続いています。
国労は「政治解決を求める」としながらも、鉄建公団訴訟原告団(297名)、採用差別国労訴訟原告団(540名)、鉄道運輸機構訴訟原告団(35名)、全動労争議団(58名)の4者がそれぞれ訴訟を提起しています。最近では、2008年1月23日に全動労争議団に対する判決が言い渡され、解雇無効の請求や、賃金、年金等の逸失利益の請求は棄却されましたが、判決は1人あたり慰謝料550万円と遅延損害金の支払いを命じました。また、3月13日の鉄道運輸機構訴訟原告団に対する判決では、解雇の効力を認めて地位確認を否定するとともに、時効を理由に、損害賠償の請求を棄却する国労側の全面的敗訴となりました。今後、控訴審を含めて審理が進む予定ですが、どのような判決が下されるかは不透明です。
原告団の訴訟の請求は、雇用(解雇無効と地位確認)、賃金、年金、退職金、慰謝料に亘り、損害賠償の金額も、その水準は、最大の原告団である採用差別国労訴訟(2006年12月提訴)の場合でも、1人あたり5,500万円(賃金、退職金、年金で3,000万円、慰謝料2,000万円)となっています。これまでの判決では、解雇無効の請求や賃金、退職金、年金などの損害賠償請求は棄却されており、勝訴した場合に慰謝料として500〜550万円の支払いが命じられていますが、これが、現時点での裁判での解決水準とみられます。国労と事件関係者は、雇用と5,000万円レベルの損害賠償を求める水準で「まとまっている」のであり、最近の集会を見ても、こうした主張は変わっていません。現下の厳しい雇用や賃金の環境の中では、この要求で世論の理解は得られるものではありません。
国労は、「四党合意」を反故にしてきた経過もあり、解決の当事者と期待する政府や政治からの信頼は地に堕ちています。民主党に対しても支援を要請していますが、このような矛盾を抱えたままで政治解決を図るのは到底困難だと考えます。行政に対する闘争団による抗議行動なども行われており、国土交通省をはじめとする当事者は、裁判決着を求める立場を全く崩していません。
国労は本年3月27日、中央労働委員会で国労とJR貨物との間で、係争事件について和解し、JR各社との紛争はなくなったことで、不採用問題の解決が近づいたと主張していますが、その認識は全く甘いと言わざるを得ません。
なお、繰り返し述べている通り、不採用問題について、「四党合意」による政治解決の道を閉ざしたのは国労自身の責任であり、2003年12月の最高裁判決で基本的には終結した問題であるという認識のもとに、労働組合として、人道的な立場から早期解決が望ましいと認識するものの、国労自らが努力して政治解決が可能となる現実的な環境を整備することが問題解決の大前提であると考えています。
さらに、JR労働界において民主化闘争の完遂こそが最大の課題であることを認識し、過激派・革マル派をJRから放逐することへの主体的な協力なしに、不採用問題の解決に対し、JR連合、JR西労組が理解を示すことは困難です。国鉄改革を通じて、国労を窮地に追い込み、不採用事件の解決を妨害してきたJR総連の姿勢や行為を見つめ直し、民主化闘争を完遂することが、真の問題解決につながることを認識するよう、強く求めたいと考えます。 |
|
|
|
○活動の基調(サブスローガンに込められた思い)
|
<サブスローガン>
|
1 「安全の再構築」「社会的信頼の回復」に向け、
一人ひとりの責任ある行動で取り組もう!
|
私たちは、公共交通機関を支える一員として日々、仕事をしています。2008年4月に策定された、「安全基本計画」はJR西日本労使のマニフェストです。今後5カ年の計画として、「絵に書いた餅」にするのではなく、現場から安全最優先の風土を創り上げなければなりません。自分たちの行動一つひとつで創り上げるものです。私たち一人ひとりの責任ある行動で安全を再構築し、失われた社会的信頼の回復に全力で取り組んでいきましょう。
|
2 男性と女性が共に生き生きと、
更に働きがいのある会社を創ろう!
|
より良い仕事をするためには生き生きと働けることが大切です。そのための職場環境の整備、風土作りにも取り組んでいかなければなりません。男性と女性が互いに信頼し安心しつ続けられる会社を目指し、「男女共同参画社会の実現」「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」の実現に向けて取り組んでいきましょう。
|
3 21世紀は、私たちの時代、
先輩からの技術とJR西労組運動を受け継ごう!
|
| 「私たち青年女性組合員の時代」はもうすでに始まっています。私たち自身が胸を張って、「JR西日本で働いてよかった!」「JR西労組でよかった!」と言える「会社」や「労働組合」を創り上げていく「責任」があります。今日まで先輩方が築いてきた、「知識」「経験」を学び技術の継承、JR西労組運動の継承を受け継いでいきましょう。 |
|
|
JR西労組「第20回定期中央本部大会」で確認した本年度の運動方針の柱
|
|
1.安全文化を確立し、真に信頼される鉄道を取り戻す
事故後に策定した「安全性向上計画」を総括し、今年3月に「安全基本計画」を策定しましたが、スタートラインに立ったに過ぎず、安全性向上計画と同様、その実行度合いや取り組み内容を現場の視点でしっかりと検証することが私たちに求められています。特に鉄道事業の分野で初めて導入した「リスクアセスメント」については、今秋以降に検証活動を行い、浮き彫りになった課題を解決し、事故再発防止に資する「リスクアセスメント」を創り上げていくことを提起します。
また、「安全基本計画」の柱の一つである、「グループ会社等との一体的な連携」についても、今日まで労働組合として主張し、取り組んできた内容ですが、昨今の労災事故の多くが、グループ会社、協力会社が関わるものであり、一刻の猶予もない状況です。「拡大安全対策委員会」、系統別の「出向者対策委員会」、あるいはJR西日本連合の取り組みを通じて、安全体制をさらに整備するとともに、その前提としての、賃金を含めた労働条件の改善や労働環境の整備を進めていくことに取り組みます。
さらには、グループ会社も含めた「安全衛生委員会」の活用を一層進めるとともに、教育や情宣活動なども通じて「安全衛生委員会」の活性化の取り組みも強化することとします。
2.JR西労組運動を次代に継承し、さらなる運動の前進を図る
今年度も1,102名の新しい仲間を迎えることが出来ました。次代を担う青年女性組合員も9,800名を超え、JR西労組全体の約4割を占めるまでに至っています。また、今日までの契約社員の導入やその正社員化、そして第二新卒採用や中途採用も始まり、組合員構成も大きく変化しており、労働組合運動の継承は重大な局面を迎えています。既に多くの平成採用の若手組合員が分会、支部の中核として活躍しつつありますが、これまで以上に青年女性委員会活動の強化が重要であるとともに、青年女性委員会活動で終わることなく、分会、支部活動を担うことのできるリーダーを育成することが今後の重要な課題であると認識しています。教育活動の充実のみならず、普段から「背中を見せる」活動を展開することを要請します。
3.民主化闘争勝利、一企業一労働組合の実現に向けて、組織の強化、拡大に総力を結集する
多くの新しい仲間を迎えた結果、組織率は90%を超えましたが、恒常的な状況ではなく、他労組からの組織拡大で、早期に確固たる90%組織を自らの手で達成し、限りなく一企業一労働組合を実現するとともに、JR西労組の運動の継承をしっかりと行うことで組織の強化を図り、安全確立の取り組みをしっかりと下支えすることが重要です。事故以降、JR総連・JR西労は、JRに働く者としての責任を完全に放棄し、安全を運動の道具にした、会社批判を繰り返しており、到底許すことは出来ません。彼らの運動に真っ向から立ち向かうことの出来る組織力をつけて実践することが、民主化支援単組として大切な取り組みだと考えます。
また、JR連合が強力に進める「民主化闘争」についても、被害者救済運動は大きく広がり、まさに結実しようとしています。引き続き中核単組として、人権を守り、JRから革マルを追放する、社会正義の闘いを進めていきます。
4.「ステップ21」を総括し、次なる企画提案運動を創り上げる
私たちJR西労組は、今日まで「力と政策」、「対立と協力」を基軸に、春季生活闘争を含めた政策課題の解決の取り組みを進めてきました。「2001年ビジョン」に続き策定した中期運動指針「ステップ21」は、福知山線列車脱線事故後に、安全文化の確立、自信と誇りの持てる職場作り、次代への継承(技術・技能、労働運動)の三大柱に再構築しました。今年度は、その総括を行い、成果と残された課題を明確にすることとし、その総括内容を基本に、高年者や女性にとって働きやすい労働環境の整備や、グループを含めた社員が働きがいや誇りの持てる賃金を含めた労働条件や労働環境の整備など、新たな政策提言を行っていきます。
5.労働組合運動への男女平等参画を進め、男女共同参画社会を実現する
労働組合における男女平等参画推進の目的は、仕事における男女平等参画を実現すること、そして男女双方の仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)、男女共同参画社会を実現することにあります。とりわけ女性の労働組合活動への参画については、今日まで青年女性委員会を中心に進めてきましたが、支部、分会などの基本組織への参画は未だ不十分な状況だと言えます。今年度以降、女性の労働組合活動への参画推進に向けて、具体的な目標を設定し、ワーク・ライフ・バランス、男女共同参画社会の実現に向けて取り組むこととします。
6.鉄道の特性を活かし、地域の活性化と地球環境保護に貢献する
私たちはJR西日本の路線の半分以上を占める地方ローカル線問題を中心に、地域活性化運動、「乗って残そう運動」を展開してきています。鉄道は地球環境に優しいと言われていますが、乗っていただいて初めてその特性を活かすことが出来ると言えます。そのためにも、自治体訪問やJR西労組地方議員団会議を通じた提言活動など、地方自治体との連携強化が必要不可欠と言えます。これまで以上の取り組みを強化し、地球環境保護に貢献することとします。
7.来るべき総選挙の勝利に全力をあげ、私たちの手に政治を取り戻す
福田政権に対する国民の怒りは爆発寸前であり、内閣支持率も低迷しており、衆議院総選挙はいつ実施されてもおかしくない情勢です。国民不在の政治に終わりを告げ、勤労者、生活者本位の民主党を基軸とする政権交代を実現するために、来るべき総選挙必勝、JR西労組が推薦する候補者の全員当選、そして組織内議員の三日月大造氏の三選に向けた取り組みを全力で進めることを要請します。
|
|
|
○具体的な取り組み
0安全・安定輸送確立の取り組み
|
2005年4月25日福知山線列車脱線事故以降、相次いだ鉄道事故から得た教訓や反省を踏まえ、「安全確立」が最重要課題となってきています。「安全性向上計画」の総括を経て、今年3月に「安全基本計画」を策定しましたが、まだスタートラインに立ったに過ぎず、安全性向上計画と同様、基本組織と一緒になって、その実行度合いや取り組み内容を現場の視点でしっかりと検証していくこととします。
二度と悲惨な事故を起こさない事を誓い「事故を決して忘れない」取り組みとして、事故現場への献花行動も積極的に行ってきました。
また、JR西労組中央本部青年女性委員会が主催した、「鉄道ユースフォーラム2008」では、事故当時復旧作業に携わった組合員の特別講義、各地方本部・総支部における「事故を決して忘れない取り組み」の発表とし、今日までの安全に対する取り組みの振り返りと、今後の活動について各地本・総支部で議論し、水平展開をすることを確認しました。
2006年6月にJR連合が策定をした「安全指針」の行動指針1でもあるように、「安全追求に妥協はない」との強い信念を持ちながら、私たちは尊い人命を預かるプロとして、日々一つ一つ着実に安全を積み重ね、JR西労組のチェック・提言機能を発揮して安全最優先の企業風土・職場風土を中心になって築きあげることが求められています。 |
|
|
第20回定期中央本部大会で決定した方針
|
| 1.「安全基本計画」の実行と検証の取り組み |
|
(1)「安全基本計画」の実行度合いの検証
労働組合の強みは、職場からのチェック・提言活動であり、福知山線列車脱線事故以降、特に重要になってきています。「安全性向上計画」の総括を経て、今年3月に「安全基本計画」を策定しましたが、まだスタートラインに立ったに過ぎず、安全性向上計画と同様、その実行度合いや取り組み内容を現場の視点でしっかりと検証していくことします。
具体的には、来春を目途に「安全基本計画」に関する実行度合いや課題などに関する検証活動を行うこととします。また、必要により三組合(JR西労組、国労西日本本部、建交労西日本鉄道本部)としての検証も併せて行います。
(2)リスクアセスメントの検証
鉄道事業分野で初めて導入された「リスクアセスメント」については、「安全基本計画」の柱であり、安全報告が積み重ねられ、職場の負担が少なく、納得性の高いものになって初めて、事故再発防止に資するものだと確信しています。しかしながら、事前の周知が十分とは言えない上に、事例が少なく評価基準がまだ少ないため、導入時期の混乱が想定されます。また、フィードバックの方法も難しく、多くの課題が発生し、今後改善を加える必要があると考えています。本部として、導入から一定期間を経た今秋以降に検証活動を行うこととします。
(3)安全職場オルグの継続
昨年の9月以降、組織強化と併せ、運転職場や工務職場などで本部オルグを実施し、安全に関する諸課題や「触車事故防止要領」に対する認識などについて意見交換を図ってきました。今年度も引き続き「安全職場オルグ」を継続し、「安全基本計画」の実行度合いや「リスクアセスメント」の浸透度合いや課題などについて、意見交換を行っていくこととします。 |
|
(1)「全てのJR関係労働者の重大労災ゼロ」に向けた取り組み
「安全基本計画」の柱の一つである、「グループ会社等との一体的な連携」については、本部としても重要な課題だと認識しており、昨今の労災事故の多くが、グループ会社、協力会社が関わるものであるという状況からも、喫緊の課題であることは言うまでもありません。
安全の基本として、まず、働く者の安全を徹底して確保することは非常に重要だと考えており、先日開催した「第3回安全シンポジウム」においても、その重要性が提起されたところです。「拡大安全対策委員会」、系統別の「出向者対策委員会」、あるいはJR西日本連合の取り組みを通じて、安全体制を一層整備するとともに、その前提としての、賃金を含めた労働条件の改善や労働環境の整備を進めていくこととします。
さらには、JR連合「安全対策会議」を活用して、JR他社や他産業の事例も参考にしながら、重大労災ゼロ撲滅に向けた提言を行っていきます。
(2)安全衛生委員会の一層の活用
教育や情宣活動等も通じて「安全衛生委員会」の活性化の取り組みを強化するとともに、グループ単組と協力して、グループ会社の「安全衛生委員会」の実態を把握しながら一層の活用を促進します。
(3)新たな政策提言
「ステップ21」の総括、そして次なる政策提言にあたり、リスクアセスメント、技術・技能の継承、教育・訓練、職場内のコミュニケーションなど、安全に関わる重要課題の実態について、職場の安全確立の視点から厳しく検証し、問題点の洗い出しなどを行い、その改善策を提言していくこととします。 |
|
本部は、引き続きJR西労組ユニオンカレッジをはじめとして、様々な機会にご遺族担当者やご被害者担当者、あるいは事故当日復旧作業に携わった組合員などの特別講義を開催し、ご遺族やご被害者、組合員自身の思いなどを伝え、胸に刻むことで事故を決して忘れない取り組みを進めることとします。
また、福知山線脱線事故以降に入社した新入社員は3千名を超え、来春にもさらに1,000名を超える社員が入社してきます。各地方本部・本社総支部をはじめとする各級機関においても、独自に事故を教訓化し、事故を決して忘れない取り組みを進めており、今後こうした取り組みを機関会議や機関紙で紹介するなど、取り組みを継続していきます。
さらには、事故を決して忘れない、そして安全最優先の意識を徹底し、安全基本計画の検証を目的として、引き続き、「安全集会(仮称)」を2009年4月25日に、JR連合と共催による「第4回安全シンポジウム」を2009年5月に開催します。 |
|
2006年1月24日、伯備線触車事故が発生し、3名の仲間の尊い命が奪われました。前述の通り、働く者の安全なくして、お客様の安全を確保することは出来ません。伯備線触車事故を受け、触車事故防止について多くの議論を経て対策を講じてきましたが、現在、恒久的対策としての「GPS式列車接近警報装置」の試使用が伯備線で行われています。安全上、改修が必要な事象は報告されていませんが、より使いやすいものとすべく現場の意見を踏まえて改修を求めていくこととします。なお、本使用に向けては、実施状況を踏まえ触車事故防止要領改訂の動向を見ながら、整理を行うこととします。また、「固定式列車接近警報装置」の設置についても、安全投資における優先的な設置を引き続き強く求めていきます。
さらには、現在試行しているアラーム機能付タイマーについても、試行結果を踏まえ、整理することとします。触車事故防止要領の改訂については、本社内での調整に時間を要している実態から、新幹線の考え方を先行して明らかにしてきました。本部は、改訂の骨子について意見交換を行いながら、関係機関から意見・要望を集約して、対応を行っているところです。今後、在来線の改訂骨子が明らかになりますが、現場の意見を反映すべく、1ヶ月程度の検討期間を確保し、会社と協議を進めることとします。 |
|
青年女性委員会は、私たちの将来に直結する中期ビジョン「ステップ21」の策定に積極的に関わってきました。そして、2002年7月に「ステップ21」が策定され、6年が経過をしました。
昨年、中間総括が行われ、今一度労働組合の原点に返り青年女性委員会としても具現化に向けた取り組みの進捗状況の確認を行いながら、私たちが中心となって活動していかなければならない次代が近づいて来ていることを認識し、今まで以上に「本気」で具現化に向けた取り組みを行っていくこととします。
具体的には、しっかりと組合員同士のコミュニケーションを取り、問題意識の共有化を図り、基本組織と青年女性委員会という「枠」を越えた活動や取り組みを実践し、「この会社で働いて良かった!!」「JR西労組で良かった!!」と思えるような活動を展開していきます。 |
|
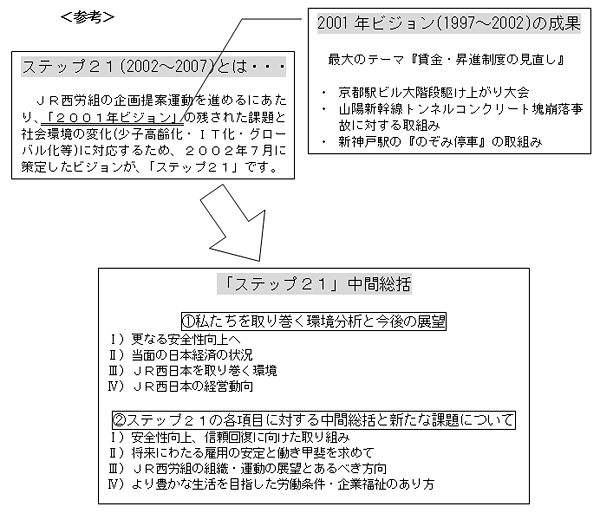
(1)男性と女性が生き生きと働ける労働環境実現のための取り組み
2008年7月1日現在、2,560名の女性組合員が、様々な職場で活躍しています。男女雇用機会均等法や労働基準法の改正により女性が活躍する職種や職場が飛躍的に増加し、育児介護休業法の改正など、仕事と家庭を両立させるための法整備も進んでいます。特に、少子高齢化を背景として成立した次世代育成支援対策推進法では、子供を育てながら働き続けるための取り組みを行うよう自治体や企業に促しています。
これまでも、女性組合員の声を反映し、ソフト・ハード両面の職場環境や結婚・出産・育児・介護など重要なライフステージを経験しながら仕事を続けることをサポートするための各種制度や労働条件について改善を図るよう会社に働きかけを行ってきました。その結果、徐々に成果が得られてきましたが、今後も労働条件の向上のため、女性組合員の意見や要望を集約していきます。
(2)「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」実現に向けた取り組み
現在、少子高齢化が深刻な社会問題となっていますが、この問題は、「社会保障不安」や「労働力不足」をはじめとして私たちの生活の様々な場面に、大きな影響を及ぼします。この解決の一つとして、仕事と生活の調和を図る「ワーク・ライフ・バランス」という考え方の必要性が言われ始めています。
2007年12月には、行政・経済界・労働界の代表により「仕事と生活の調和」憲章が策定され、「仕事と生活の調和」実現に向けて取り組むことが宣言されました。この課題に対しては、男性も女性も共に取り組んでいくことが肝要であり、JR西労組青年女性委員会も、これと同じ歩調を取っていきます。
その取り組みの一つとして、今後も、JR連合の「単組女性代表者会議」をはじめとした働き方に関する各種勉強会に積極的に参加し、他単組・他産別の制度を勉強していき、「総合労働協約改定交渉」等を通じて、「仕事と生活の調和」実現に向けた労働条件を整備・改善・向上させる取り組みを行っていきます。
また、こういった取り組みについて、男性組合員も女性組合員も共に積極的に考えていくために、各種会議の場を通じて、情報の共有化を図っていきます。
(3)組合活動における男女平等参画実現に向けた取り組み
男女共同参画社会実現に向け、各種労働条件を向上させていくためには、男性と女性が共に現状と課題を理解し、労働組合活動に参画し、その様々な活動を通じて意見や要望等を出し合って集約していくことが重要であり、それを実現するための取り組みを行っていくことが不可欠です。
しかしながら、これまでの組合活動スタイルを振り返ってみると、男性中心となることが多く女性にとって活動しにくい場面が多々ありました。そういった反省を踏まえ、今年度、JR連合では女性組合員の積極的な活動を促すため、「男女平等参画推進計画」が策定されました。この計画では、今までの組合の活動スタイルを振り返り、具体的な活動の指針が示されました。
中央本部青年女性委員会では、この計画を踏まえた取り組みを行っていきます。特に、女性役員のサポートをしていく取り組みとして、基本組織の女性役員も交えた勉強会を行い、情報の共有化を図っていきます。
また、医療系統については、医療フォーラム等を通じて比較的年代にかかわらず声を集約してきましたが、鉄道系統については、青年女性委員会の組織の構成上、30歳以上の女性組合員の声を反映しにくかったという現状を踏まえ、30歳以上の女性組合員の意見を聞いていく取り組みを行っていきます。 |
|
(1)支部・分会青年女性委員会の整備と世話役活動の充実
JR西労組運動や、青年女性委員会活動を少しでも「楽しくて、身近なもの、絶対に必要な労働組合」として感じてもらうために、引き続き青年女性委員会が一定人数所属する支部、分会の青年女性委員会組織の整備と活動の充実を図っていきます。
本年度も、多くの支部・分会で新たに青年女性委員会が結成され、レク活動や勉強会をはじめとする各種取り組みだけでなく、選挙活動についても積極的に行ってきました。それらの取り組みを通じて活動内容の浸透や、種々の活動に対する参画、情報伝達や広報活動の充実、先輩・後輩・同期といった人間関係の構築と、一人一人の組合員とのコミュニケーションを大切にし、悩みへの対応などのよりきめ細やかな世話役活動の充実を図っていきます。
また、基本組織の執行委員を務める青年女性組合員も増えてきました。青年女性委員会の枠だけでなく、JR西労組運動の次代へのリーダーとなるべく、思いや実務の「継承」にも取り組んでいきます。
(2)新入・転入組合員に対するフォローの充実
青年女性委員会の大きな役割の一つに「新入組合員」の加入、歓迎のための取り組みがあります。
共に働き、活動する仲間づくりのために、青年女性組合員の意見をより大きな声・チカラにするために、希望や不安を抱いて入社する新入社員の気持ちを感じ取り共に働く仲間として温かく迎え入れることは大変重要です。新入社員全員の加入実現に向けて取り組むと共に新入社員向けPRパンフレットや「YOU’S」特集号の作成をするほか、各職場へ配属後の歓迎会や勉強会等を通じ、転入組合員の歓迎会等のフォローを行っていきます。
また、20歳を迎える青年女性組合員に対しては、JR西労組としての「記念品及びメッセージ」を作成、進呈する取り組みを行い、各地本では地本主催の「成人式」等のセレモニーの実施を引き続き要請します。
(3)中央本部主催のレクリエーションの開催
中央本部は各地本・総支部と力を合わせ、お互いに意見を出し合いながら開催地本の特色のある内容の充実にも努め、引き続き組合員の相互交流を目的とした、レクリエーションを開催します。なお、2008年9月20日〜21日に福岡地本で開催を予定していた、「ユーススピリット」については台風13号の影響により中止の決断をしました。2009年については再度、福岡地本の主管で開催をしていきたいと考えています。日程については、関係地方本部と調整のうえ決定をしていきます。
(4)情宣活動の充実
【1】青年女性委員会情報誌「YOU’S」と「YOU’SMailnews」
の発行・配布活動
中央本部では、業務に関わる情報の紹介や青年女性委員会に関わる情報を各地本・総支部、支部、分会に発信し、全青年女性組合員に周知できるように「YOU’S」を随時発行してきました。また、迅速でより正確な情報を提供するために、「YOU’SMailnews」の発行もおこなってきました。引き続き、中央本部主催の各種行事の開催予定や、各種業務課題に対する取り組み、各支部、分会青年女性委員会の紹介などを掲載し、みなさんに親しみをもってもらえるような編集、発行、送付、配布、掲示等についても工夫し努力をしていきます。
また、青年女性委員会の活動をJR西労組組合員全体に知ってもらうための取り組みとして、JR西労組新聞・JR西労組ニュースへの投稿も引き続きおこない、一人でも多くの組合員に青年女性委員会の活動を知ってもらえるような取り組みを展開していきます。
【2】「ホームページ」の活用(http://www.jrw-union.gr.jp)
現在、より一層充実したJR西労組のホームページの中に、青年女性委員会の情報発信ページ「青年女性委員会かわら版」を設けています。内容は、今後の活動紹介や、イベントや行事情報の提供を楽しく見ていただけるように、写真もたくさん使って掲載しています。また「YOU’S」「YOU’SMailnews」のバックナンバーも掲載し、みなさんに情報提供を行っています。
これからの課題としてはより多くの青年女性委員会のみなさんにこのホームページを知ってもらうことはもとより、内容の充実を含め、見ていただく組合員に楽しんでもらえるように、更に努力を重ねてよりよいホームページとなるように取り組んでいきます。
【3】「JR西労組ダイレクトニュース」の発行
昨年から開始した新たな取り組みとして、「JR西労組ダイレクトニュース(携帯電話へのJR西労組情報のメール配信)」がありますが、まだまだ登録者数が少ない状態(10月現在の登録者1,082名)にあり、スピーディーな情報伝達の利点を活かした利用ができていない状況にあると言えます。JR西労組の交渉の経過や自分達に大切な情報源の取得方法として特に青年女性組合員に対しての登録者数拡大を重点的に行います。
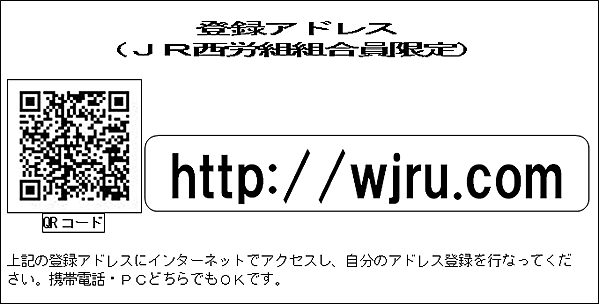
【4】各級青年女性委員会レベルでのニュースなどの発行促進
各地本・総支部はもとより、各支部、分会の青年女性委員会でも機関紙の発行に取り組んでいます。これらがより一層活性化する為の一つの手段として、中央本部主催「機関紙コンクール」を開催しています。引き続き機関紙コンクールを開催し、お互いの情報交換を行います。
|
|
JR西労組は、私たちの働くJR西日本をよりよくするために、日夜現場で奮闘しています。そして、JR西労組をこれからも更に維持・発展させていくには、私たち青年女性委員会の力が不可欠になっています。JR西労組と会社がお互いに発展していくため、中央本部青年女性員会として、以下の取り組みを行います。
(1)「ユニオンカレッジ」への参加と参画
今まで会社を支えていたベテランが退職されJR西日本の社員は年々減少しています。私たち青年女性組合員は、仕事で使う技術の「継承」のみならず、労働運動の「継承」についても考えなくてはなりません。青年女性組合員がこれからのJR西労組運動の一翼を担うという「自覚」のもと、私たちの中から新しいリーダーを育てるために、これまで開催してきた『ユニオンカレッジ』も継続していかなくてはなりません。
具体的には『青年女性委員会コース』や『女性役員コース』『ニューリーダーコースⅠ・Ⅱ』『特設コース』にも引き続き受講生として参加します。
今年は、これまでは地方本部・本社総支部が主体的に行ってきた「ユニオンスクール(新入組合員コース)」について、「ユニオンスクール(新入組合員半年後研修)」と明確に位置づけ、全新入組合員を対象に地本本部・本社総支部主催(中央本部共催)で開催します。また、一層の安全確立に向け、安全衛生委員会の活性化を目的とする学習会を開催します。
そして、事務局・事務局研修生としてもユニオンカレッジに参加し、教育活動の進め方について学び、組合活動の「継承」を実践する手段を学んでいきます。
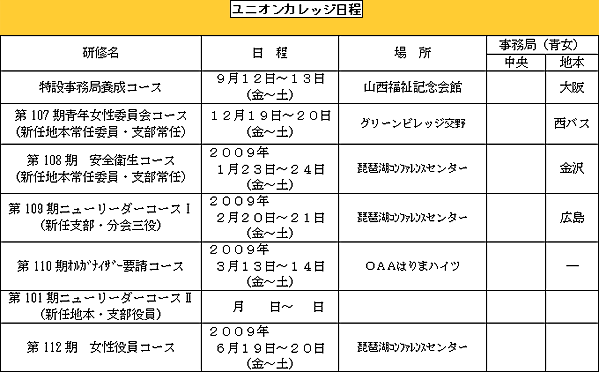
(2)中央本部青年女性委員会主催の学習会等の開催
【1】「中央ユースフォーラム」の開催
「中央ユースフォーラム」は、「バスユースフォーラム」「医療系統ユースフォーラム」「鉄道ユースフォーラム」の3つがあり、それぞれ系統・職種ごとの課題や問題点等を共有化するとともに、特有のテーマについて意見交換し合いながら、「将来の会社や私たちの職場について考える場」として開催してきました。
「バスユースフォーラム」「医療系統ユースフォーラム」は関係地本・総支部の主体的な準備により年々内容を充実し、「鉄道ユースフォーラム」においても活発なディスカッションが繰り広げられています。来年度も引き続き、「鉄道ユースフォーラム2009」「医療系統ユースフォーラム」「バスユースフォーラム」を開催します。
これからも進め方や内容を工夫しながらアンケート結果や中央常任委員会で議論し、みんなで考え、各フォーラムの充実を目指します。「鉄道関連」については来年度も福知山線列車脱線重大事故を意識して「安全」についても考えるものにしたいと考えています。また、「医療系統ユースフォーラム」「バスフォーラム」についても、例年通り開催します。
【2】「第9回地方ローカル線活性化意見交換会」の開催
地方交通機関、とりわけ鉄道のローカル線がLRT化等の検討により社会的にクローズアップされる中で、私たちの「地方ローカル線」に対する取り組みも一層重要度が増してきています。
「地域社会の発展」「JR西日本の将来の経営」「私たちの職場」を考えるうえで重要なキーワードとなる「地方ローカル線」について、青年女性委員会の視点で、そのあり方について議論し、活性化に向けたアイデアの提案や実践活動を行っていくことが重要であるとの認識のもと、これまで8回の「地方ローカル線活性化意見交換会」を開催してきました。
JR西労組の「地域活性化」の取り組みを理解するとともに、地域の行政や利用者、私たちにできることについての意見交換など、内容を充実させながら開催することとします。(準備地本に和歌山地本を予定しています。)
【3】「新大総合指令所組合員との意見交換会」の開催
「新大阪総合指令所組合員との意見交換会」は、2005年から始めた活動で、日頃あまり顔を合わせず仕事をしている新大阪総合指令所組合員と京都、大阪、和歌山、神戸地本の各系統の青年女性組合員を集め、日頃から疑問に思っていることなどを率直に意見交換し、お互いの業務内容や日々の疑問を解決する場として役に立っています。開催当初は乗務員と新大阪総合指令所組合員との意見交換でしたが「他の系統でも開催してほしい」との要望があり、第4回目より乗務員以外の系統(駅・施設・電気)でも開催し、計19回を数えるまでになりました。
今後もよりよい意見交換会を開催するために、京都、大阪、和歌山、神戸地本と本社総支部及び新大阪総合指令所分会と協議し、今後のあり方について適宜検討していきます。
(3)「春季生活闘争」「総合労働協約改訂交渉」を通じた青年女性組合員の要求の実現
春の「春季生活闘争」や秋の「総合労働協約改訂交渉」は、賃金、労働時間、休日、福利厚生といった私たちの労働条件や日々の生活に大きく関わってきます。これまでも、厳しい経済・経営状況の中、JR西労組の組織力で青年女性組合員に関係する多くの成果を勝ち取ってきています。こうした労働組合の取り組みや行動に対して、青年女性委員会としても、各種フォーラムや学習会・意見交換会等で出た声やアンケートで集約した意見をもとに、青年女性委員会の思いを実現させるべく、それぞれ参加できる単位において、積極的かつ主体的に関与・参加・参画していきます。 |
|
(1)産別の「JR連合青年・女性委員会」活動への積極的な参加
【1】JR連合青年・女性委員会主催「第14回ユースラリー」への参加
JR連合青年・女性委員会主催の「ユースラリー」は「JRグループで働く仲間同士の交流」を目的に開催されています。第14回のユースラリーは「JR東海ユニオン」の準備のもと開催となります。
そして、全国のJR連合の仲間達との交流と絆を深め、「元気印」のJR西労組青年女性委員会をアピールしましょう。
|
|
「第14回ユースラリー」
日 時:2008年5月頃(未定)
場 所:山梨県(早川町周辺)
準備単組:JR東海ユニオン
|
|
【2】「民主化行動」への積極的な参加・参画
JR連合が最重要組織課題として取り組む「民主化行動」に対しては、JR西労組青年女性委員会としても社会正義の観点から、また今後の健全な労働運動や労使関係を構築する観点から積極的に取り組んでいかなければなりません。
昨年の7月17日には「東労組組合員役員らによる脱退・退職強要事件(浦和事件)」が東京地裁において、被告7名全員に有罪判決を言い渡しました。JR連合としてもこの判決を民主化闘争完遂の「追い風」として取り組み、「民主化闘争完遂への道筋を必ず具現化させる」との決意の下、節目の年度として位置づけることとしています。
今年度も引き続き、JR総連が多数を占めるJR東日本・JR北海道・JR貨物といった会社にいる仲間に激励を行っていくとともに、各種教育やイベント、情報や資料等を活用した民主化行動の必要性や重要性を学ぶ教育等を実施していきます。具体的には、JR東日本ユニオン・JR北労組・貨物?産労と連携をとりながら、民主化行動に積極的に参加をしていきます。
【3】地方協議会の組織整備
西日本エリアにおいては、私たちJR西労組青年女性委員会が先頭に立って各「地方協議会」の活動、そしてそれを通じた「地方連合会」の活動に参加・参画し、行動範囲や視野を広げるとともに、JRの労働者を代表する産別「JR連合」をしっかりアピールしていくことが重要です。今年度も引き続き、JR連合の「各地方協議会」における青年女性委員会の組織整備と、今ある組織の活動の充実と活性化を図り、地方レベルにおける連合の諸活動に積極的に参加・参画していくこととします。
また、JR連合加盟単組主催のレクリエーション等のイベントにも、各地方協議会を通じ、情報伝達を行い、積極的に相互参加しながら身近な地域交流も促進していくこととします。
【4】JR連合を通じた「連合中央(地方連合会)」活動への積極的な参加・参画
私たちJR西労組は、産別である「JR連合」を通じて「連合(ナショナルセンター)」に加盟しながら、より働きやすい、暮らしやすい社会を目指して全国レベルの各種政策課題に取り組んでいます。
そして連合の地方組織である「地方連合会」には、JR連合加盟各単組が地域ごとに組織する「都道府県協」を通じて参画し、青年委員会や女性委員会への役員派遣、メーデーをはじめ平和行動や選挙活動への参加などを通じて地域ごとの交流を深め、連帯を高め合ってきました。
「JR連合」を通じたこれらの活動により、大きな課題に取り組むだけでなく、今以上に行動範囲や視野を広げるとともに、より多くの仲間と交流を深めるべく、引き続き積極的な参加・参画を継続していきます。
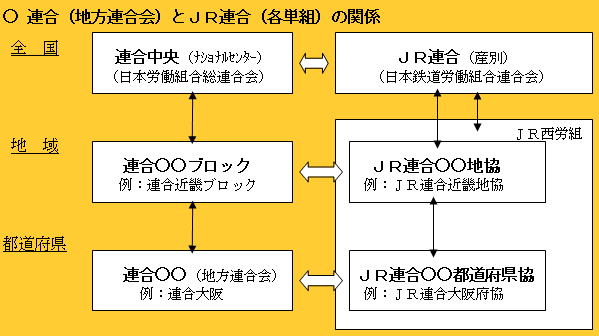
(2)「JR西日本連合青年女性連絡会」との連帯・連携強化
連結決算時代の中、グループとしての経営が評価される昨今、JR西日本グループ全体の発展と私たちの豊かな暮らしのために、JR西日本グループに所属する関連労組(47単組)で組織する「JR西日本グループ労働組合連合会(略称:JR西日本連合)」と、その中の青年女性委員会組織で集う「青年女性連絡会」を通じてよりよい会社づくり・働きやすい職場づくりに取り組むことが重要です。12月には、JR西日本連合青年女性連絡会は、1年間の活動を振り返り、次年度の活動方針を決める「定期総会」にも積極的に参加・参画するとともに、JR連合主催のユースラリーや各単組のレクリエーション等の各種イベントに相互に参加し、グループ労組の仲間とさらに交流と連帯を高める取組みを行っていきます。
|
レクリエーション「チーム対抗交流ボーリング大会」
「第9回定期総会」
日 時:2008年12月14日(日)
場 所:新大阪丸ビル(新大阪イーグルボール等)
|
(3)社会貢献活動の実施
【1】使用済みプリペイドカード回収ボランティアの継続実施
「使用済みプリペイドカードの回収」を通じた国際貢献活動ですが、今年も「6,687枚」(昨年度28,427枚)を回収することができました。集まったカードは、JR連合を通じて「JOICFP(家族計画国際協力財団)」へ送付され発展途上国の生活改善に役立てていただいています。
JR西労組青年女性委員会では、誰もが気軽に参加できるボランティア活動ということで、引き続き「使用済みプリペイドカード回収」に取組んで行きます。
【2】みんなが参加できる地域社会への貢献活動の検討・実施
今までの社会貢献活動としての具体的な実績では、「使用済みプリペイドカードの回収」を通じた国際貢献活動や「Jフェスタ」で募った募金を「吹田市緑化基金」「あしなが育英基金」へ寄付することでチャリティー活動にも参加してきました。
さらなる地域社会への貢献を目指し、(財)オイスカと大阪府、四條畷市と協力し、四條畷市にある「ふれあいの森」で「『団結』ふれあい森づくり」と称して、ボランティア活動を中期的に計画し実施します。今までの「使用済みプリペイドカード」の回収と合わせ、森林整備を行い、自然と触れ合い、レクリエーション等も交えながら、環境問題に対する意識の向上を図り、青年女性組合員相互の交流と繋がりを大切にするボランティア活動を目指します。 |
|
|
6政治活動への参画について・来るべき総選挙勝利に向けて取り組み
|
|
1.基本方針
私たちの運動の理念・政策・目的などに理解を示し、支持・賛同する議員との関係を強化し、政治的課題の解決にむけて取り組むこととします。
2.政治活動の考え方
政治活動は「非自民、反共産」を原則として、連合、JR連合の政治路線を基本に取り組むこととします。
議員および政党とのつながりは、政治的課題の解決を目的として、JR西労組の綱領、運動方針、政策課題に理解を示し、支持・賛同する者との協力関係を強化します。
(1)国政選挙への対応の考え方
【1】JR西労組の政治の基本方針、当面する政治活動の考え方を前提に、取り組みを進めます。
【2】選挙活動は、組織内において混乱を生じさせないことを最優先し、組織の団結とJR西労組の発展
を第一義に取り組みます。
【3】「政治対策委員会」を継続して設置し、具体的対応を協議しながら取り組みを進めます。
【4】組織面に次いで、推薦候補の基本方針を重視することとします。
【5】組織内議員を抱える労働組合として、社会的責務を認識し推薦候補必勝の取り組みを展開します。
<推薦候補の基本方針>
【1】連合・JR連合の推薦候補とします。
【2】過去の経緯を尊重しつつ、JR西労組の綱領・運動方針に賛同する政治家個人を推薦します。
【3】JR西労組の方針に基づき地方本部が推薦する候補者は、中央執行委員会で組織としての推薦を決定します。
(2)政治顧問について
【1】今後も三日月衆議院議員を「政治顧問」として、組織内での政治活動に参加、アドバイスをしてもらうこととします。
【2】政治団体「JRみかづき会」と連絡体制を強化し、三日月大造衆議院議員の政治活動について、可能な限り協力を行っていくこととします。
(3)地方選挙への対応の考え方
私たちの地域活性化の取り組みなど、JR西労組議員団会議との連携を深めながら、私たちの政策課題の解決のために積極的に取り組むこととします。
<推薦候補の基本方針>
【1】JR西労組議員団会議の会員が立候補する場合は、組織内公認候補として選挙闘争を進めます。
【2】会員以外の立候補者の推薦・支持は、地方本部・支部の決定に基づきます。
(4)投票行動の徹底
政治の改革のためには、まず、社会の構成員として国民の義務である投票を行う必要があります。JR西労組として、機関紙や分会機関などを通じて組合員、家族への方針の理解と投票の徹底(期日前投票の啓蒙)、棄権の防止を呼び掛け、政治参加の促進を引き続き積極的に進めることとします。
3.議員団会議との連携強化
(1)JR西労組地方議員団会議
地域に密着した鉄道業に従事する私たちにとって、地方政治は非常に大切な役割を担っています。特に運動の柱である地域活性化の取り組みには、自治体や住民の参加、協力が不可決と考えます。現在JR西労組地方議員団会議には21名の会員が結集しており、JRと働く仲間の立場を代弁しながら、地域に密着した政治活動を展開しています。
しかしながら、地方議員団会議結成時からすると高齢化、市町村合併などの影響もあり所属議員は減少傾向にあります。地方議員団の重要性に鑑み引き続き会員の選挙の勝利と、議員団会議の質的強化にむけて取り組むとともに、組織内議員の拡大に向けて地方本部と連携を蜜にしながら、積極的な展開を図ることとします。
(2)JR連合国会議員懇談会
JR連合国会議員懇談会は現在8名で構成しています。引き続きJR労働運動の民主化と過激派の排除の問題など、国政での私たちの政策実現にむけ、JR連合国会議員懇談会議員との連携を強化していくこととします。
また、昨年2月21日に発足した「21世紀の鉄道を考える議員フォーラム」は、新たな議員の加入もあり、現在、衆議院議員53名、参議院議員21名で構成し、政策課題を中心に積極的に活動を展開しています。
今後ともJR西労組の政治方針に基づき、上記加盟議員を中心に関係も強化し、政治的課題の解決にむけて取り組みます。
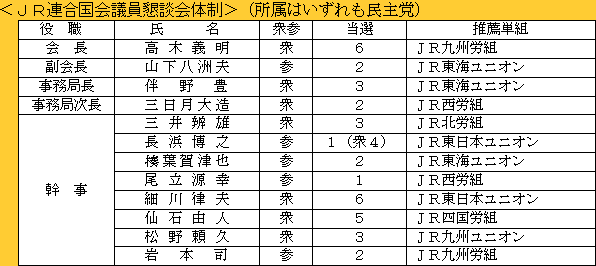
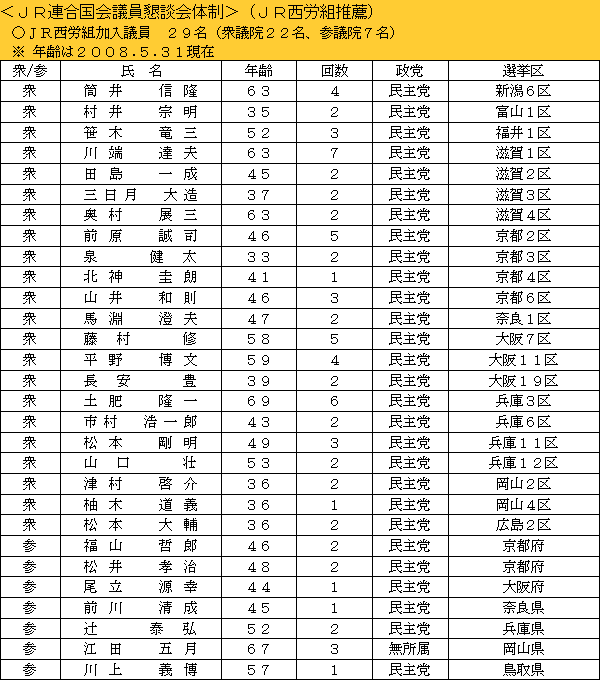
4.来るべき総選挙勝利に向けた取り組み
(1)候補者の推薦
候補者の推薦にあたっては、連合・JR連合の推薦候補を基本とし、JR西労組の綱領・運動方針に賛同する政治家個人を推薦することとします。各地方本部の推薦に基づいて中央執行委員会で推薦を決定します。現時点で51名の推薦決定をしています。(第20回定期中央本部大会時点)
(2)選挙体制の整備
既に2008年第5回執行委員会(11月19日)で、本部内に倉橋中央執行委員長を本部長とする、第45回衆議院議員「選挙対策本部」を設置しました。今後、情勢を見ながら、支援の取り組みなどを具体的に進めることとします。特に、JR連合国会議員懇談会議員を最重点候補、「21世紀の鉄道を考える議員フォーラム」議員を重点候補に位置づけ、必勝の取り組みを行います。
(3)組織内候補予定者「三日月大造(みかづきたいぞう)氏」必勝の取り組み
滋賀県第3区から立候補予定である、組織内候補「三日月大造氏」については、現在国土交通委員会理事として、JR連合、JR西労組が抱える政策問題、安全問題の課題解決あるいは働く者の代弁者として日々奮闘されているところですが、三日月氏3期目当選に向けて、「みかづき会」加入拡大を含め、JR西労組の組織力を発揮し、全力を傾注することとします。具体的な取り組みについては、「選挙対策本部」で検討することとします。
|
|
上記の活動を進めていくために、機関会議としての「中央常任委員会」を月に1回定例開催します。中央本部主催の各行事等の企画や検討、運動の取り組みの深度化、各地本・総支部の取り組みの共有化等を図るとともに、役割分担を明確にし、各地本・総支部の代表である中央常任委員が責任を持って取り組める体制とします。
また、引き続き中央本部三役を中心として、各地本・総支部主催の常任委員会・レクリエーション・女性フォーラム・ユニオンスクール等にも積極的に参加していきます。また、組織強化を目的とし、分会や支部の行事にも積極的に参加し「よく見える」労働組合「JR西労組運動」の深度化を図り、より緊密な情報交換ができるような取り組みを行います。
また、「拡大常任委員会」を必要の都度開催し、「中央本部、地本・総支部三役合同会議」についても開催します。そこで、新体制での年間スケジュールの徹底や活動の中間総括を行い、「春季生活闘争」「総合労働協約改訂交渉」に向けた要求集約なども合わせて行っていきます。 |
|
|
|
|
|